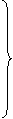○城南衛生管理組合公文例規程
昭和50年11月27日訓令甲第9号
城南衛生管理組合公文例規程
(目的)
第1条 この規程は、城南衛生管理組合(以下「組合」という。)の公文書作成に必要な一般の基本的事項を定め、文書を標準化することにより、事務能率の向上と適正化を図ることを目的とする。
(文書作成の原則)
第2条 組合の公文書作成は、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。
(文書作成の要領)
第3条 組合において作成する文書の形式は、すべて左横書きとし、その要領は、
別表文書作成要領による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月29日訓令甲第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年5月29日訓令甲第4号)
この規程は、平成7年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日訓令甲第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
文書作成要領
目次
第1 文体
第2 用字
第3 用語
第4 用紙の用い方及びとじ方
第5 文書の構成・書き方
1 文書番号
2 日付
3 あて名
4 発行者名
5 題名
6 本文
7 公印
8 その他
第6 法規文書
1 条例
2 規則
3 条例(規則)の構成
4 条例(規則)の書式
第7 令達文書
1 訓令
2 命令
3 指令
第8 公示文書
1 告示
2 公告
第9 一般文書
1 往復文書
2 儀礼文書
3 その他の文書
第10 内部文書
1 辞令
2 復命書(報告書)
3 願・届
第1 文体
1 公用文の文体は、原則として「である」体を用いる。ただし、公示及び掲示の類並びに往復文書の類は、なるべく「ます」体を用いる。
2 文章は、口語文を基調とした平明なものとする。
3 文章は、なるべくくぎって短くし、接続詞や接続助詞などを用いて文章を長くすることは避ける。
4 文の飾り、あいまいなことば、まわりくどい表現はできるだけやめて、簡潔な論理的な文章とする。敬語についても、なるべく簡潔な表現とする。
第2 用字
1 漢字は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)による。ただし、地名、人名等固有名詞についてはこの限りでないが、さしつかえない限り仮名書き又は簡易字体を用いる。
2 常用漢字表で書き表せないものは、次により書きかえ、言いかえをする。
(1) かな書きにする。
例 遡る → さかのぼる 搗く → つく
(2) 当用漢字表中の音が同じで意味の似た漢字で書きかえる。
例 車輛 → 車両 傭人 → 用人
(3) 同じ意味の漢語で言いかえる。
例 捺印 → 押印 采配 → 指揮
(4) やさしいことばで言いかえる。
例 抹消する → 消す 抵触する → ふれる
(5) 他によい言いかえがなく、かな書きにすると誤解されるおそれがあることばは、その部分だけかな書きにする。
例 右舷 → 右げん 口腔 → 口こう
3 漢字で書くことができることばでも、次のものについてはできるだけかな書きにする。
(1) 代名詞、副詞、接続詞、助動詞、助詞、接頭語及びこれらに準ずるもの
(2) 外国の地名、人名及び外来語
(3) 動植物の名称(ただし当用漢字で認められているものは、さしつかえない。)
(4) 熟字を訓で読む場合及び当て字
例 団扇 → うちわ
(5) 漢字の意味が本来の意味からかけはなれているとき。
例 有難い → ありがたい 粗末 → そまつ
(6) 漢字で書くと誤解されるおそれがあるとき。
例 工夫 → くふう 大勢 → おおぜい
4 かなは、ひらがなを用い、かたかなは、外国の地名、人名及び外来語に限って用いる。ただし、外来語であってもその意識の薄くなっているものは、ひらがなで書く。
例 タバコ → たばこ カルタ → かるた
5 仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)による。
6 送りがなは、送りがなのつけ方(昭和48年内閣告示第2号)による。
7 数字は、特別な場合を除きアラビア数字を用い、その用い方は、次のとおりとする。
(1) 漢数字を用いる場合
ア 固有名詞 例 四国 九州 二重橋
イ 概数を示す語 例 二、三人 四、五人 数十人
ウ 数量的な意味の薄い語 例 一般的 一部分 第三者
エ 単位として用いる語 例 億 万
オ 慣習的な語 例 一休み 二言目
(2) 数字の区切り方は、3位区切りとし、区切りには、「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号など順数を表す数には区切りをつけない。
(3) 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。
区分 | わるい書き方 | よい書き方 |
小数 | 0123 0.123 | 0.123 | 小数点を書く 小数点も1字分として書く |
分数 | 1/2 |  2分の1 2分の1
| 分数の線はまっすぐに書く |
帯分数 | 11/2 | 
| 〃 |
(4) 日時、時刻及び時間の書き方は、次の例による。
区分 | 日付 | 時刻 | 時間 |
普通の場合 | 昭和49年3月12日 | 8時30分 | 8時間 |
省略する場合 (文章中には用いない。) | 昭和49、3、12 昭 49、3、12 | 8:30 | |
(5) 期間を表す場合において、暦の月等と混同されるおそれのある場合は「カ」を用いる。
例 3カ月(3ケ月とはしない。)
8 符号及び記号は、主として文章の構造や語句の関係を明らかにするために用い、その種類及び用い方は、次のとおりとする。
(1) 「、」(てん・読点)
読点は、文章中のことばの切れ目や続きを明らかにする必要のあるところに用いる。ただし、多く用いすぎて全体の関係が不鮮明にならないよう注意する。
ア 主語(主部)に続く「は」、「も」、「が」などのあとには、さしつかえない限り用いる。
イ 文章のはじめにおく接続詞及び副詞のあとに用いる。
例 ただし、 たとえば、
ウ 対等に並列する語句の間に用いる。ただし、接続詞(及び・又は)助詞(と・や)などで結ぶ場合は用いない。
エ 並列する語句が2つの場合は、接続詞で結び、他は読点で結ぶ。
例 管理者、副管理者、助役及び収入役
オ 接続詞の前には用いない。
(2) 「・」(なかてん)
ア 外国語、外来語のくぎりに用いる。
イ 日付、時刻、称号などを略して表す場合に用いる。
例 昭47・10・1 N・H・K
ウ 名詞を並列するとき「、」のかわりに用いる。
エ 名詞以外の語句を列挙するとき、数詞を並列するときには用いない。
(3) 「( )」(かっこ)
ア かっこは、語句又は文章に注記を加えるとき又は見出し記号をはさんで用いる。
イ かっこ書きの中で更に必要のあるときは「〔 〕」(そでかっこ)又は「(( ))」(ふたえがっこ)を用いることがある。
(4) 「「 」」(かぎ・かぎがっこ)
ア 会話又は語句を引用するとき、あるいは特に示す必要のある語句をはさんで用いる。
イ かぎ書きの中で更に必要のあるときは、「『 』」(ふたえがぎ)を用いる。
(5) 「.」(ピリオド)
ア ピリオドは、数字の単位を示す場合に用いる。
イ 略称符号として「なかてん」と同様に用いる。
(6) 「,」(コンマ)
ア 数字の三位区切りに用いる。
イ 横書きの場合に読点として用いることもある。
(7) 「:」(コロン)
コロンは、次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。
(8) 「~」(なみがた)
この記号は「・・・から・・・まで」を示す場合に用いる。
例 東京~京都 第1条~第3条
(9) 「・・・・・」
語句の代用などに用いる。
(10) 「―」(ダッシュ)
語句の説明や言いかえなどに用いるほか、地番などを省略する場合に用いる。
(11) 「→」(やじるし)
左のものが右のものに(やじるしの方向に)変わることを示す場合に用いる。
(12) 「々・ゝ・ゞ・

・〃」(くりかえし符号・おどり字)
ア くりかえし符号は「々」以外は使用しない。ただし、簡易な表などでは「〃」(ののじ書き)を用いてもよい。
イ 「々」は、漢字1字のくりかえしの場合に用いる。
例 人々 日々 三々五々
ウ 異った意味を表す場合は用いない。
例 民主主義 学生生活
(13) 傍点・傍線
傍点は語句の上に、傍線は語句の下に書く。
例 ハッキリと 能率的に
(14) みだし記号
ア 箇条書で項目を細分する場合は、次の順序で記号を用いる。
| 第1・・・・・順数 |
| 1 |
| (1) |
| | ア・・・・・五十音 |
| | (ア) |
| | a・・・・・アルファベット |
| | (a) |
イ 見出し記号は句読点をうたず、記号の位置は、細分するにしたがって1字づつあけて書く。
(15) 「?」・「!」(疑問符・感嘆符)
疑問符・感嘆符は、原則として用いない。
第3 用語
1 公文書を平易な感じのよいものとするため、特殊なことばやかたくるしいことばを用いず、日常一般につかわれているやさしいことばを用いる。
2 言いにくいことばを使わず、口調のよいことばを用いる。
3 音読することばはなるべく避け、耳で聞いて意味のすぐわかることばを用いる。
例 陳述する → 述べる 充填する → うめる
4 音読することばで意味の2様にとれるものはなるべく避け、ほかの同じ意味のことばを用いる。
例 協調する → 歩調をあわせる (「強調する」とまぎれやすい。)
5 同じ内容(意味)のことを違ったことばで言い表わさないよう統一する。
例 理由・事由 → 理由 改訂・改定 → 改定
第4 用紙の用い方及びとじ方
1 用紙は・日本工業規格A4判(210㎜×297㎜)、B5判(182㎜×257㎜)及びB4判(257㎜×364㎜)を用いる。ただし、別に規格を定めている場合その他必要のある場合はこの限りでないが、できるだけA判系列のものを使用する。
2 用紙の用い方は、原則としてA4判及びB5判はたて長に、B4判は横長に用いる。
3 文書のとじ方は、A4判及びB5判をたて長に用い左とじとし、B4判の用紙は2つ折り又は3つ折り込みとする。ただし、特別な場合のとじ方は、次のとおりとする。
(1) A4判及びB5判以外の用紙のとじ込みは、適宜折りたたみ、又は台紙に貼りつける等、A4判又はB5判に揃えるようにする。
(2) A4判及びB5判の用紙を横長に、B4判用紙をたて長に用いた場合は、上部をとじてもさしつかえない。ただし、この場合もB4判については、できるだけ折りこむようにする。
(3) たて書きの文書のみをとじる場合は、右とじとする。
(4) 左側に余白のあるたて書きの文書は、そのまま文書の左をとじる。
(5) たて書き文書で左に余白のないものやふくろとじをしたものは、うらとじ(背中合わせ)とする。
第5 文書の構成・書き方
1 文書番号
(1) 文書番号は、文書の日付、題名とあわせて文書の同一性を示すために表示するもので、文書の種類を示す語句(条例、告示等)とあわせて用いる。
(2) 文書番号は、文書の種類により設けられた文書整理簿により順を追ってつける。ただし、軽易な文書にあっては、文書番号を省略する場合がある。外部への文書は、原則としてすべて文書番号を付するものとする。
(3) 文書番号の書き出しは、文書の左側に書くとき(例規文書、公示文書その他)は第1字目とし、往復文書など文書の右側に書くときは日付と揃えるようにする。
(4) 書式により、文書番号の定位置が示されていないものは、できるだけ文書の右上方とし、特に体裁を重んじる文書、その他余白のない文書は、文書の構成を考えて適当な位置に表示する。
2 日付
(1) 文書の日付は、記載事項の効力に係るものであり、すべての文書に明記しなければならない。
(2) 文書番号とともに文書の整理簿により処理し、適当にさかのぼったり、さきゆきの日付を用いることのないようにしなければならない。
(3) 往復文書の日付は、文書番号の次に文書の中央右よりに、文書番号と揃えて書き出し、その末尾が終りから2字程空くようにする。
(4) 往復文書以外の文書(公告式関係、契約書等)は、通常本文の次に書き、その初字は第3字目とする。
3 あて名
(1) あて名は、原則として相手側の職、氏名を掲げるが、氏名を省略し、職名のみでもさしつかえない。官庁の名称(例 ○○市、○○局)のみの表示は用いない。
(2) 敬称は、一般に「様」を用いる。ただし、令達文書(命令書・辞令)には敬称を付さない。
(3) あて名の位置は、文書の日付の次、発信者のまえに書き、その初字は第1字目とする。ただし、令達文書の場合は、本文の前に文書の中央右よりに書き、末字が終わりから2字程度空くようにする。
(4) わく罫のある用紙を用いる場合は、公印がわく内に押印できるよう位置に注意する。
4 発行者名
(1) 文書の発行者名は、記載事項の責任の所在を明確にするため、すべての文書に明記する。
(2) 必ず職氏名を表示するが、庁内文書の場合は職名のみでもさしつかえない。ただし、正式の行政手続の場合は、この限りでない。
(3) 発行者名は、あて名の次(令達文書、公告式関係は日付の次)に、文書の中央右よりに書き出し、その末字が終わりから2字程度空くようにする。
(4) わく罫のある用紙を用いる場合は、公印がわく内に押印できるよう位置に注意する。
5 題名
(1) 題名は、文書の内容がわかるよう簡潔なものとし、往復文書の類は、末尾に文書の性質を表すことば(照会・通知等)をかっこ書きしてつけ加える。
(2) 題名は、通常左右3字空けて書く。ただし、これによりがたい場合は全体のつりあいを考えて中央にくるよう配字する。
6 本文
(1) 本文は、書き出し及び行を改めたときは、1字あけて2字目から書き出し、2行目は第1字目から書く。
(2) 「ただし」、「この場合」などで始まるものは、行を改めない。ただし、「なお書き」や「追って書き」は行を改める。
なお、「なお書き」と「追って書き」を同時に使用する場合には、「なお書き」を先に使用する。
(3) 1行の字数及び行間隔は、全体のつりあいを考える。
(4) みだし記号の初字は、第1字目とし、記号から1字あけて書き出す。2行目以下は、みだし記号の次の位置から書く。
(5) 項目を細分するみだし記号は、細分するに従って1字づつ空けて書く。
7 公印
(1) 公印は、文書の真実性を表すものとして、原則としてすべての施行文書に押印する。
(2) 公印は、文書の施行者(発行者)名の最終の文字にかかるように押印する。
(3) 契約書、証明書など重要な文書で2枚以上にわたる場合は、とじあわせを割印する。
(4) 文書が施行されたこと及び発行件数を明確にし、かつ、偽造を防止するために、すべての施行文書について契印を押印する。
(5) 契印は、原議書を下にし、文書の上端中央に原議書と半分づつ押印する。
(6) 発行数が2以上の場合は、原議書等にあて先を記入し、交付先を確認しながら契印を押印する。
8 その他
(1) 「下記のとおり」などとして本文と区別するために書く「記」は、文書の中央に書く。
(2) ふりがなは、当該字句の上(たて書きの場合は右)にひらがなで書く。
(3) 字句の訂正は、誤りの部分を2本線で消し、その上部に正しく書きかえる。
(消しゴムやその他の修正液で消してはならない。)
数字の場合は、一つの文字だけでなく数全部を訂正する。
(4) 訂正部分には、施行者の欄に押印した公印を押印する。
第6 法規文書
1 条例
(1) 組合の条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき、法令及び府の条例に違反しない範囲内で組合の事務に関し、議会の議決を経て制定する法規をいう。
(2) 組合の条例で規定する事項は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する事務のほか組合の組織及び運営に関することである。
(3) 管理者の専属的権限に属する事項については、条例で定めることができない。(規則で定める。)
(4) 条例又は規則のいずれで定めるべきかの定めのない事項については、どちらで定めてもよいが、一般に議会の議決が必要と思われる事項は、条例で規定する。
2 規則
(1) 組合の規則とは、地方自治法第15条の規定に基づき、管理者が法令及び条例に違反しない範囲内で、その権限に属する事項について制定する法規をいう。
(2) 規則で規定する事項は、管理者の専属的権限事項である。
(3) 条例の制定及び議会の議決を要する事項であっても、条例の委任がある場合及び条例を施行し、又は議会の議決を経た事務の執行について必要な場合は、規則を制定することができる。
3 条例(規則)の構成
(1) 公布文
公布文は、条例を公布する旨の公布者の意思を表明するもので、公布する旨の文章と公布年月日及び公布者の職氏名で構成される。公布者の氏名は、公布者が署名する。(公印の押印は不要)
×○○○条例(条例の題名)をここに公布する。 | |
××元号○○年○○月○○日 | |
| 城南衛生管理組合 |
| 管理者 ○○○○×× |
(2) 条例番号
ア 暦年ごとに、公布の順にしたがって、新設、改廃の別なく一連番号で表示される。
イ 一部改正が行われても既存の条例の番号はかわらない。
(制定時の番号で表示する。)
(3) 題名
ア 内容を簡潔に表示し、できるだけ「城南衛生管理組合」を冠せる。
なお、他の法令等とまぎらわしくないようにする。
城南衛生管理組合○○条例・城南衛生管理組合○○に関する条例 |
イ 改廃の場合は、既存の条例名をその題名中に掲げる。
城南衛生管理組合○○○条例の一部を改正する条例・城南衛生管理組合○○ |
○条例を廃止する条例 |
(4) 目次
ア 本則の内容が複雑で、編・章・節などに分けて作成した場合、内容の理解と索引を容易とするため目次を置くものとする。
イ 目次は、編・章・節ごとにそれに属する条文の範囲を括弧書きで示す。この場合、条文が3以上の場合は「―」又は「~」でつなぎ、2条の場合は、「・」でつなぐ。
ウ 目次は、題名の次に書き、その初字は第1字目とする。以下見出し記号の要領で1字ずつあけて書く。
目次 | |
×第1編 | |
××第1章×○○○(第○条・第○条) | |
××第2章 | |
第1節×○○○○(第○○条~第○○条) | |
第2節×○○○(第○○条~第○○条) | |
×第2編 | |
××第1章 | |
第1節×○○○(第○○条) | |
×附則 | |
(5) 本則
ア 本則は、条例で制定しようとする実質的な内容を成文化した部分で、条例の本体である。
イ 本則は、一般に「条」によって構成するが、必要により「条」を「項」に、「項」を「号」に、その他の細分をする。
ウ 箇条書による細分のほか、「前段」「中段」「後段」「ただし書」などに分けて規定することがある。
エ 項は第2項目から2・3……………と順を追って表示し、第1字目に書き、号は第1号目から(1)・(2)・(3)…………と表示し、第2字目に書く。
以下の細分は見出し記号の用い方による。
オ 内容が簡単なものは、条を用いず項のみとする。この場合、項が2項以上のときは第1項目から1・2・3…………と表示し、1項のみのときは項番号を付さない。(附則の場合主としてこの方法を用いる。)
カ 各条文の規定する内容の理解を容易にするため、原則として1条ごとに条文の見出しをつけるものとする。ただし、連続する2以上の条文が同一の事項について規定しているときは、先の条文にまとめてつける。
キ 条文の見出しは条文の上に括弧書きし、括弧の書き出しは第2字目とする。
ク 条文中に他の法令等を引用する場合は、その法令等の名称の次に公布年及び法令番号を括弧書きで表示する。同一の条例中に同一法令を2度以上引用する場合は、最初の引用時のみに表示する。この場合同時に括弧内に略称を表示することにより、2度目以下の引用は略称を用いることができる。
○○○○法(昭和○○年法律第○○号。以下「法」という。) |
ケ 本則中の編・章・節などの区分は、編の初字を第3字目とし、以下前記の目次の配字と同様に1字ずつあけて書き出す。
コ 内容の複雑な表や様式は、「別表」及び「別記様式」として本則中では省略し、附則の次に掲げる。
(6) 附則
ア 附則は、本則の内容に関し、附随的事項を規定する部分であり、その規定する事項及び順序はおおむね次のとおりである。
(ア) 条例の施行期日
(イ) 既存の条例の廃止
(ウ) その条例の施行に伴う経過措置
(エ) 既存の条例の改正
(オ) その他本則に書くことを適当としない事項
イ 附則は、項(複雑な場合は条)に分けて規定し、その書き方は、本則の書き方による。
ウ 附則には、必要により見出しをつけるものとする。
エ 附則の「附」の字は第4字目、「則」の字は第6字目とする。
4 条例(規則)の書式
(1) 一般的形式(新しく制定する場合は、この形式による。)
城南衛生管理組合条例第○○号 | | 条例番号 |
×××○○○○○○○条例 | | 題名 |
目 次 | 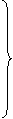
| |
×第1編×○○○○○ | |
××第1章×○○○(第○条~第○○条) | 目次 |
××第2章×○○○○(第○条~第○○条) | |
×附則 | |
×××第1編×○○○○○ | | |
××××第1章×○○○ | | |
×(○○○) | | 条見出し |
第1条×○○・・・・・・・・・・ | | 条文 |
×○○○○○○・・・・・・・・・ | | |
×(○○○○) | | |
第2条×○○○○・・・・・・・・ | | |
×(1)×○○○○・・・・・・・ | | |
(2)×○○○○・・・・・・・ | | |
2×○○○○○・・・・・・・・ | | |
(略) | | |
×××附×則 | 
| 附則 |
1×○○○・・・・・・・・・・・・ |
2×○○○○・・・・・・・・・・・ |
(2) 既存の条例の廃止
×○○○条例(元号○○年城南衛生管理組合条例第○○号)は、廃止する。 |
(3) 既存の条例の一部改正の場合
題名の次に、次のような前文(柱書き)を置き、改正内容に応じて、次のア又はイに掲げる柱書きをその次に加え、新旧対照表又は改正文を書く。
×○○○条例(元号○○年城南衛生管理組合条例第○○号)の一部を次のように改正する。 |
×次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 |
×次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 |
(4) 2以上の条例を同時に改正する場合
ア 改正する条例ごとに「条」に分けて規定する。
イ 書き方は、他と同様であるが、条に分けるため、書き出しは1字多くあける。
×××○○○条例等の一部を改正する条例 |
×(○○○条例の一部改正) |
第1条×○○○条例(元号○○年城南衛生管理組合条例×第○○号)の一部を次のように改正する。 |
××次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄×に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 |
| 改正後 | 現行 | |
| ×(○○) | ×(○○) | |
| 第○条×・・・ | 第○条×・・・ | |
| ×△△△・・。 | ×○○○・・。 | |
×(○○○○○条例の一部改正) |
第2条×○○○○○条例(元号○年城南衛生管理組合条×例第○号)の一部を次のように改正する。 |
××次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄×に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 |
| 改正後 | 現行 | |
| ×(○○) | ×(○○) | |
| 第○条×・・・ | 第○条×・・・ | |
| ×△△△・・。 | ×○○○・・。 | |
|
(5) 題名を改正する場合
(6) 条文を改正する場合
ア 1条(項・号)全部を改正する場合
(ア) 条を改める場合
改正後 | 現行 |
×(△△△) | ×(○○○) |
第○○条×△△△ | 第○○条×○○○ |
×△・・・・・。 | ×○・・・・・。 |
(イ) 項を改める場合
改正後 | 現行 |
×(○○○) | ×(○○○) |
第○○条×略 | 第○○条×略 |
2×略 | 2×略 |
3×△・・・・・。 | 3×○・・・・・。 |
(ウ) 号を改める場合
改正後 | 現行 |
×(○○○) | ×(○○○) |
第○○条×略 | 第○○条×略 |
2×○○○ | 2×○○○ |
×(1)×略 | ×(1)×略 |
×(2)×△・・・。 | ×(2)×○・・・。 |
イ 1つの条(項・号)を2つ以上に分割する場合は、既存の条(項・号)の全文を改正し、同じにその後に1条(項・号)を追加する。
ウ 字句を改正する場合
(ア) 1つの条の場合
改正後 | 現行 |
×(○○○) | ×(○○○) |
第○○条×△△△・・・。 | 第○○条×○○○・・・。 |
(イ) 複数の条において同じ字句を改める場合
改正後 | 現行 |
×(○○○) | ×(○○○) |
第○○条×△△△・・・。 | 第○○条×○○○・・・。 |
×(○○○) | ×(○○○) |
第○○条×△△△・・・。 | 第○○条×○○○・・・。 |
(ウ) 1つの条において複数の字句を改める場合
改正後 | 現行 |
×(○○○) | ×(○○○) |
第○○条×△△△・・・ | 第○○条×○○○・・・ |
×△△・・。 | ×○○・・。 |
2×略 | 2×略 |
3×△△△△・・・。 | 3×○○○○・・・。 |
(エ) 条例中、同じ字句を一括して改める場合
改正後 | 現行 |
×(○○○) | ×(○○○) |
第○○条×△△△・・・。 | 第○○条×○○○・・・。 |
2×△△△・・・。 | 2×○○○・・・。 |
×(○○) | ×(○○) |
第○○条×・・△△△・・。 | 第○○条×・・○○○・・。 |
(7) 条文を追加する場合
ア 条(項・号)を中間に加える場合
(ア) 以下の条番号を繰り下げる。
改正後 | 現行 |
×(○○○) | |
第2条×○○○・・・・・。 | |
×(○○○) | |
第3条×○○○・・・・・。 | |
×(○○○) | ×(○○○) |
第4条 | 第2条 |
×略 | ×略 |
第5条 | 第3条 |
×略 | ×略 |
第6条 | 第4条 |
×略 | ×略 |
第7条 | 第5条 |
×略 | ×略 |
(イ) 枝番号を付する。・・・他の条例等に引用している条文は、繰り下げると、それらの条例等を整理する必要があり、混乱を避けるため多くはこの方法を用いる。
改正後 | 現行 |
×(○○) | ×(○○) |
第2条×略 | 第2条×略 |
×(○○) | |
第2条の2×○○○。 | |
第3条×略 | 第3条×略 |
イ 条(項・号)を末尾に加える場合
ウ 条文中に後段、ただし書、字句を加える場合
(ア) 後段を加える場合
改正後 | 現行 |
×(○○○) | ×(○○○) |
第○○条×・・。△△△△△×△△△△。 | 第○○条×・・。 |
(イ) ただし書を加える場合
改正後 | 現行 |
×(○○○) | ×(○○○) |
第○○条×・・。ただし、△×△△△△。 | 第○○条×・・。 |
(ウ) 字句を加える場合
改正後 | 現行 |
×(○○○) | ×(○○○) |
第○○条×・・・・・○○×○△△・・・。 | 第○○条×・・・・・○○×○・・・。 |
(8) 条文を削除する場合
ア 中間の条(項・号)全文の削除
(ア) 「削る」とする場合・・・以下の条を繰上げ整理する必要がある。
改正後 | 現行 |
| ×(○○) |
| 第3条×○○○○。 |
×(○○○) | ×(○○○) |
第3条×略 | 第4条×略 |
×(○○○○) | ×(○○○○) |
第4条×略 | 第5条×略 |
×(○○○○○) | ×(○○○○○) |
第5条×略 | 第6条×略 |
(イ) 「削除」とする場合・・・改正後も「第○条 削除」として条そのものはなお存置し、繰上げ整理の必要がない。
改正後 | 現行 |
第○条×削除 | ×(○○○) |
第○条×・・・。 |
(ウ) 通常、項及び枝番号の最後の条を削る場合や、繰上げの簡単なときは(ア)を用い、章(節)を削るときや、繰上げの必要な条文を削るときは(イ)を用いる。
イ 末尾の条(項・号)を削る場合
ウ 条文中のただし書や字句を削る場合
(ア) ただし書を削る場合
改正後 | 現行 |
×(○○○) | ×(○○○) |
第○○条×・・。 | 第○○条×・・。ただし、×○○○○。 |
(イ) 字句を削る場合
改正後 | 現行 |
×(○○○) | ×(○○○) |
第○○条×・・・・○○○×▽▽▽。 | 第○○条×・・・・○○○×△△▽▽▽。 |
(9) 附則の書き方
ア 施行期日
(ア) 公布の日から施行する場合
(イ) 将来の特定の日から施行する場合
×この条例は、元号○○年○○月○○日から施行する。 |
×この条例は、公布の日から起算して○○日を経過した日から施行する。 |
×この条例は、○○法(元号○年法律第○号)施行の日から施行する。 |
(ウ) 施行期日を規則に委任する場合
×この条例の施行期日は、公布の日から起算して○○日を超えない範囲内に |
おいて規則で定める。 |
(エ) 一部の施行期日を異ならせる場合・・・異なる部分の施行に関する事項はただし書で書く。
×この条例は、○○○から施行する。ただし、第○○条の(第○○条に関す |
る改正)規定は、○○○から施行する。 |
イ 適用について
適用とは現実に発生した事実に対し、条例等の規定の効力を発生させることであり、一般には施行の日を明確にすることによりその日から効力を発することになるが、次のような場合に用いる。
(ア) 具体的な対象をより明確にする場合
×この条例は、○○○から施行し、○○○○から(○○について)適用する。 |
(イ) 遡及適用の場合
×この条例は、○○○から施行し、元号○○年○○月○○日(○○○○○○) |
から適用する。 |
ウ 既存の条例等の改廃(同一の法形式のものに限る。)
(本則の改廃と同じ)
エ 経過措置
経過措置は、条例の制定、改廃により混乱が生じないよう、移り変わりを円滑に行わせるために定めるものである。
×この条例の施行前に旧条例の規定によりされた○○については、なお従前の |
例による。 |
×この条例の施行の際現に○○であるものは、この条例による○○とみなす。 |
オ 有効期限に関する規定
×この条例は、元号○○年○○月○○日まで、その効力を有する。 |
×この条例は、元号○○年○○月○○日限り、その効力を失う。 |
×この条例は、施行の日から起算して○○年を経過した日にその効力を失う。 |
改正後 | 現行 |
×××附×則 | ×××附×則 |
別表(第○条関係) | |
| ○○○ | | |
| |
改正後 | 現行 |
×××附×則 | ×××附×則 |
| 別表(第○条関係) |
| | ○○○ | |
| | | |
改正後 | 現行 |
別表(第○条関係) | 別表(第○条関係) |
| 略 | | | 略 | |
| △△△ | | | ○○○ | |
| 略 | | | 略 | |
| | | | | |
改正後 | 現行 |
別表(第○条関係) | 別表(第○条関係) |
| 略 | | | 略 | |
| ○○ | | | | |
| | | | | |
改正後 | 現行 |
別表(第○条関係) | 別表(第○条関係) |
| 略 | | | 略 | |
| | | | ○○○ | |
| | | | | |
(11) その他
次に掲げる場合において、改め文方式による改正をすることができる。
ア 一の例規中に多数存在する同じ語句を一括で改正する場合
(例1)
×○○○条例(元号○年城南衛生管理組合条例第△号)の一部を次のように改正する。 |
×「○○」を「△△」に改める。 |
(例2)
×○○○条例(元号○年城南衛生管理組合条例第△号)の一部を次のように改正する。 |
×本則中「○○」を「△△」に改める。 |
(例3)
×○○○条例(元号○年城南衛生管理組合条例第△号)の一部を次のように改正する。 |
×第○章中「○○」を「△△」に改める。 |
(例)
×別表を次のように改める。 |
別表(第○条関係) |
| ○○○・・・。 | |
ウ 表、
別表、様式等の改正において、当該改正内容が新旧対照表の中に収まらない場合
エ 引用条項のズレを修正する改正に限る場合
(例)
×第△△条中「第○○条」を「第○○条の2」に改める。 |
オ その他新旧対照表方式による一部改正により難いと認める場合
第7 令達文書
1 訓令
(1) 訓令とは、行政機関が本来有する指揮監督権又は法律により与えられた特別の権限に基づいて、下級の機関又はその職員に対し、権限の行使又は職員の服務について指揮する命令をいう。(効力の範囲は、指揮権の及ぶ範囲に限られる。)
(2) 訓令甲
ア その内容を例規の形式をもって定め、職務の運営、処理について命令するものをいう。
イ その改廃は訓令甲により行う。
ウ 書式
城南衛生管理組合訓令甲第○○号 | 訓令番号 |
×○○○○規程を次のように定める。 | 制定文 |
××昭和○○年○○月○○日 | | 発令年月日 |
| 城南衛生管理組合 | 発令者職氏名 |
| 管理者 ○○○○  |
×××○○○○規程 | | 題名 |
(略) | | |
(注)1 必要により令達先を入れることがある。
2 公印を押印する。
3 題名以下の書式は条例・規則と同じ。
(3) 訓令乙
ア 職員を指揮監督するため、服務心得などについて命令するもので、例規の形式をとらないもの。
イ 書式
城南衛生管理組合訓令乙第○○号 | | 訓令番号 |
| ○○○○ | 令達先 |
×××○○○○○について | | 題名(みだし) |
×○○○○・・・・・・・・・・ | 命令事項 |
(略) | | |
××昭和○○年○○月○○日 | | 発令年月日 |
| 城南衛生管理組合 | 発令者職氏名 |
| 管理者 ○○○○  |
(注)1 令達先は省略してもよい。
2 命令事項についての細部や付記事項は発令者名の次に記することもある。
2 命令
(1) 命令とは、行政機関が権限に基づいて一方的に特定の相手方に対し、特定の事項を指示し、命令することをいう。
(2) 相手方の意思にかかわらず、一定の義務を課し、又は権利や利益を奪うものであり、その命令について法令等の根拠を明確にする。
(3) 命令に対して不服のある場合、不服申立て等の方法について記しておくのが普通である。
(4) 書式
城南衛生管理組合命令第○○号 | | 命令番号 |
| ○○○○○○ | | 令達先 |
×○○○○について、○○○○により(次の理由により)○○ | | 命令事項 |
○○○する。(命ずる 禁ずる 取り消す) | | |
××昭和○○年○○月○○日 | | 命令年月日 |
| 城南衛生管理組合 | 
| 命令者 |
| 管理者 ○○○○  | 職氏名 |
| 記 | | 
| 付記 |
理由 | | |
1 ×○○○・・・・・・ |
2 ×○○○・・・・・・ |
(注)1 あて名は敬称を付さない。
3 指令
(1) 行政機関がその権限に基づき、相手方からの出願に対して、許可、不許可等の行政行為を行い、又は指示することをいう。
(2) 軽易なものにあっては、改めて指令書を発行せず奥書の形式をとる場合もある。(申請書の末尾等余白に書きこむ方法)
この場合、申請書は2部提出させ又は「写し」をとり、必ず控えとして1部保管する。
(3) 書式
ア 一般的形式
城南衛生管理組合指令第○○号 | |
| (指令先)○○○○○ |
×昭和○○年○○月○○日(相手方文書番号)で申請のあった○○○○につ |
いては、(次のとおり)○○する(許可・承認する) |
××昭和○○年○○月○○日 | |
| 城南衛生管理組合 |
| 管理者 ○○○○  |
記 |
(内容・理由・許可条件等) |
(注)1 あて名には敬称を付さない。
イ 奥書の場合
城南衛生管理組合指令第○○号 | |
×申請(願い)のとおり認可(承認)する。 | |
××昭和○○年○○月○○日 | |
| 城南衛生管理組合 |
| 管理者 ○○○○  |
(注)1 あて先の記載は不要
2 無条件で認める場合にのみ用いる。
第8 公示文書
公示とは、行政機関が一定の事項を公表し、広く一般に周知させるための手続で、告示と公告がある。
1 告示
(1) 告示は、行政機関が法令の規定又は権限に基づいて、処分又は決定した事項を公示する場合に行う。
ア 法令等で告示することが規定されているもの
イ 法令等に規定されていないが、公示することが必要と認められるもの(主として行政に関する事項について)
(2) 告示は、公示するためのものであり、法規的なものと異なり、一般には住民を拘束しないものである。ただし、法令等の委任による場合は、その範囲内において拘束力をもつ。
(3) 書式
その内容を規程の形式をもって定める場合と、単に周知の形式をとる場合がある。
ア 規程の形式を用いる場合
城南衛生管理組合告示第○○号 | 告示番号 |
×(○○○○(根拠法令等)の規定に基づき、)○○○規程 | 制定文 |
を次のように定める。(定めた) | |
××昭和○○年○○月○○日 | | 告示年月日 |
| 城南衛生管理組合 | 告示者職氏名 |
| 管理者 ○○○○  |
×××○○○規程 | | 題名 |
(略) | | |
(注)1 題名以下は、条例・規則と同じ書式
イ 単に周知する場合
城南衛生管理組合告示第○○号 | | 告示番号 |
×××○○○○○○について | | 題名 |
×○○○○(根拠法令等)の規定により○○○○○○○○○ | 告示文 |
する。 | |
××昭和○○年○○月○○日 | | 告示年月日 |
| 城南衛生管理組合 | 告示者職氏名 |
| 管理者 ○○○○  |
記 | |
(略) | |
2 公告
(1) 一定の事実を多数の人に周知させるために公示する場合に行う。
ア 法令等で公告することが規定されているもの。
イ 法令等に規定されていないが、公示することが必要と認められるもの(試験の実施、証票類の無効宣言、公売の実施、その他)
(2) 周知させるための手段であり拘束力はもたない。ただし、場合によっては、対応する適切な手段を怠ったために不利益を受けることがある。
(3) 書式は、告示に準ずる。
第9 一般文書
1 往復文書
(1) 往復文書とは、一般に一定の事項の連絡のために発する文書で、次のような場合に用いるものをいう。
ア 照会・回答・通知・報告
イ 諮問(一定の機関に対し意見を求めること。)
ウ 答申(諮問に対して意見を述べること。)
エ 進達(上級機関への申請等を中継して送達すること。)
オ 副申(進達等に際し、意見を添付すること。)
カ 申請(許認可等、相手方に一定の行為を要求するときに提出するもの。)
キ 届(単に知らせるもので、申請のように相手方に行為を求めるものではない。)
ク 建議(行政機関に対し、意見や希望を申し出ること。)
ケ 通達(下級機関や職員に対し、職務上の指示をするもの)
(2) 書式
| 文 書 記 号 番 号 |
| 昭和○○年○○月○○日 |
あて先 様 | |
| 城南衛生管理組合 |
| 管理者 ○○○○  |
×××件名○○○○○(○○) | |
×本文○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○ |
○○○○○・・・・ | |
2 儀礼文書
(1) 式辞(式辞・訓辞・祝辞・弔辞・答辞)
ア 式辞とは式典等に際して述べることばをいう。
イ 本来は話しことばであるが、文書にして主催者側に渡すのが普通である。
ウ 話しことばであるため、公印は用いない。
エ 書式は一般の慣習によるが、おおむね次のとおりとする。
管 理 者 名 | × × 昭 和 年 月 日 | | | ○ ○ ○ ○ ○ | × 本 文 ○ ○ ○ ○ | | 祝 辞 | |
(注)1 用紙は一般に巻き紙を用い、巻き紙の場合は必ずたて書きとする。
2 最初に「祝辞」等式辞の目的を書く。ただし、上書きのある場合は省略してもよい。
3 巻紙は書き終わりから中に巻き込み(又は適宜折り込み)、上包みはまず左を、次に右を折り、上下を折る。
4 上包みには式辞の目的を書く。
5 あて名は書かない。
(2) 書簡類
礼上、あいさつ状等儀礼上発する文書は、一般の私信と同形式による。ただし、事務処理の一環として発する礼状等は往復文書の形式による。
(3) 賞状の類
賞 状 |
| 氏 名 | 様 |
×1等賞 | | | |
○○○○・・・・・・ | | | |
××昭和○○年○○月○○日 | | | |
| 城南衛生管理組合 |
| 管理者 ○○○○  |
(注)1 最初に「表彰状」、「感謝状」等顕彰の目的を記し、「賞」の場合は、あて名の次に賞の種類を書く。
2 句読点は付さない。
3 本文の書き出しは第1字目とする。
3 その他の文書
(1) 契約書(覚書、協定書その他契約に準ずるもの)
ア 契約とは、申込みと承諾の二つの意思表示が合致することにより成立する法律行為をいう。
イ 契約は、当事者が対等の立場で締結するものである。
ウ 契約締結後の変更は、必ず変更契約を行い、先の契約書を訂正してはならない。
エ 書式
×××○○○○○契約書 |
×○○○○(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、 |
○○○について次のとおり契約を締結する。 |
×(○○○) | |
第1条×○○○○・・・・ | |
(略) | |
×この契約の成立を証するため、この契約書○通を作成し当事者(及び保証 |
人)が各1通を所持する。 | |
××昭和○○年○○月○○日 | |
| 甲 ○○○○ ○○○○  |
| 乙 ○○○○ ○○○○  |
(注)1 標題は単に「契約書」とせずに、一見して内容がわかるように「○○○○○契約書」とする。
2 前文には契約当事者を記載(甲乙、その他の記号等で略称を表示する。)し、契約の目的を簡単に記する。
3 本文には、契約の目的、金額、支払方法、数量、履行期限、危険負担、紛争解決の方法、その他必要事項を順次詳細に、箇条書にする。
4 後文は、当事者が契約書を所持する旨の文章で結ぶ。
5 特にあいまいな表現や、誤解を生じるようないいまわしをしてはならない。
6 相手方の印は、必ず登録済の印(実印)を押印させるようにする。
7 添付書類のある場合は、それらをとじこんで1通の契約書とみなす。
(2) 請願書(陳情、要望その他これらに準ずるもの)
ア 請願は、その事項を所管する官公署に必ず文書で提出しなければならない。
イ 議会に対する請願は、その議会の議員の紹介を必要とする。
ウ 書式
×××○○○○○○○○に関する陳情書 | |
×本文○○○・・・・・ | |
○○○○・・・・・・・ | |
××昭和○○年○○月○○日 | |
あて先 様 | |
| 城南衛生管理組合 |
| 管理者 ○○○○  |
(注)1 標題は内容がわかるようにする。
2 請願の場合、紹介議員の氏名等は、別紙にしてとじ込むか表紙に書き、請願者、あて先、請願内容と混同しないようにする。
(3) 議案
議案は、議会の審議を求めるため提出するもので、必ず提案理由を添付する。
議第○○号 | |
×××○○○○○○○○○○について | |
×○○○○・・・・・ | |
○○○○・・・・・・ | |
××昭和○○年○○月○○日提出 | |
| 城南衛生管理組合 |
| 管理者 ○○○○ |
提案理由 | |
×○○○○・・・・・ | |
○○○○・・・・・ | |
(注)1 本文はごく簡単にし、具体的な内容は別に付記し、又は別紙に書く。
2 提案理由は、別紙又はページを改める。
(4) 争訟関係文書
行政機関の処分その他権力の行使による行為に関し不服を申し立てるものや、それに対する行政機関の決定等に関係するものをいう。
審 査 請 求 書 |
×(審査庁)○○○○ 殿 | |
審査請求人 | 住 所 |
| 氏 名 印 |
1×審査請求に係る処分の内容×○○○・・・・・ |
2×審査請求に係る処分があったことを知った年月日×○○○・・・・・ |
3×審査請求の要旨×○○○・・・・・ |
4×審査請求の理由×○○○・・・・・ |
5×処分庁の教示の有無及びその内容×○○○・・・・・ |
6×添付書類×○○○・・・・・ |
7×○○○○×○○○ |
裁 決 書 |
×審査請求人 ○○○○ 殿 |
×審査請求人から請求のあった○○○○については、次のように裁決する。 |
×主文 |
×○○○○・・・・・ |
×事案の概要 |
×○○○○・・・・・ |
○○○○・・・・・ |
×審理関係人の主張の要旨 |
×○○○○・・・・・ |
○○○○・・・・・ |
×裁決の理由 |
×○○○○・・・・・ |
○○○○・・・・ |
××○○年○○月○○日 |
| 城南衛生管理組合 |
| 管理者 ○○○○ |
(注) 箇条書にして、内容を明確にする。
(5) 証明書
ア 証明書は、特定の事実を公に証明するもので、客観的に確認できる資料に基づいて発行しなければならない。
イ 新たに証明書を発行しないで、奥書の形式をとる場合もある。
ウ 書式(奥書の場合)
×上記のとおり(願いのとおり)相違ないことを証明する。 |
××昭和○○年○○月○○日 | |
| 城南衛生管理組合 |
| 管理者 ○○○○  |
第10 内部文書
1 辞令
(1) 辞令とは、任命権者が職員の身分、給与、その他人事上の事項について、本人に命令するための文書をいう。
(2) 辞令書は、一般に個人に交付するが、一括して作成し、該当者に周知できる方法による場合もある。
(3) 書式
| 職員の身分(職名)氏 名 |
(命令内容)○○○○を命ずる |
××昭和○○年○○月○○日 |
| 城南衛生管理組合 |
| 管理者 ○○○○  |
(注)1 辞令用紙を用い、句読点は付さない。
2 2以上の事項について同じに行うときは、連記して発令する。
3 連記する場合は、次の順序による。
(1) 身分に関する事項
(2) 職務に関する事項
(3) 給与に関する事項
(4) 所属に関する事項
(5) 期間に関する事項
(6) その他の事項
4 職員以外への委嘱状には敬称を付する。
5 書出しは第1字目とする。
6 職員の身分や職名は発令について基礎となった身分、職名であり、出向、併任、役職による任命等の場合は注意する。
(4) 辞令文
ア 身分
イ 職務
ウ 給与
エ 所属
オ 出向・・・出向とは、同一の団体内で任命権者を異にする機関への異動で、出向命令と出向先での任命の2つの行為により完成する。出向先での任命後は、他の職員と同じである。
カ 併任・・・現在の身分を保有させたまま、他の職員の身分を取得させることをいう。
キ 派遣・・・他の団体との間における人事交流で、現在の身分を保有するが、通常派遣先で併任される。
ク 委嘱・・・職員以外の者を付属機関の委員等に任命する場合
ケ 嘱託・・・委嘱する対象が事務事業の場合
コ 兼職・・・現在の職を有したまま他の職務を命ずる場合
サ 職務代理・・・職務の代行であるが、その職に属する権限が与えられ、実質的にはその職の者が行ったと同じ効果を生じる。上位の職を代行する場合
(○○○が○○○のため不在中)○○○の職務代理を命ずる |
シ 事務取扱・・・下位の職の職務を代行する場合
ス 休養・・・職員の病気により職を休ませる場合
休職・・・職員の分限処分により職を休ませる場合
○○○(根拠法令等)の規定により○○○(期間)休養(休職)を命ずる |
セ 復職・・・休養(休職)していた者を職務に従事させる場合
ソ 退職・・・本人の意思による場合
タ 免職・・・本人の意思にかかわらず職を免ずる場合
チ その他一定の事項を命ずる場合
2 復命書(報告書)
(1) 復命とは、命じられた用務の結果等を報告することをいう。
(2) 特に書式が定められていない場合は、起案用紙により処理してもよい。
3 願・届
願・届とは、職員が、服務上の事項について、上司の許可を受ける場合又は届け出るよう定められている場合に作成するものをいう。
 ・〃」(くりかえし符号・おどり字)
・〃」(くりかえし符号・おどり字)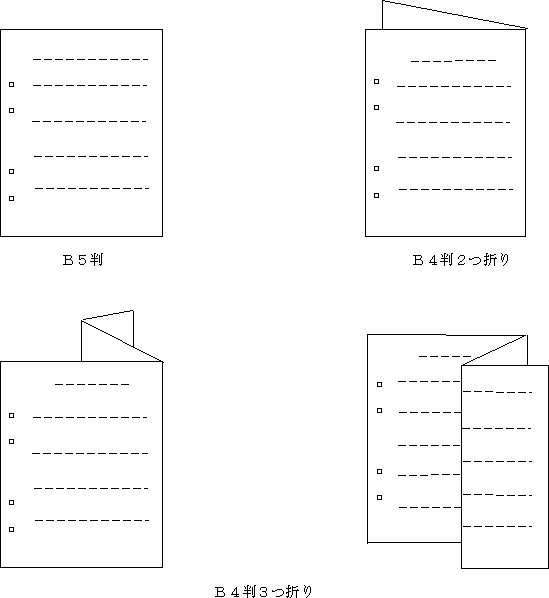
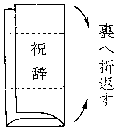
 2分の1
2分の1